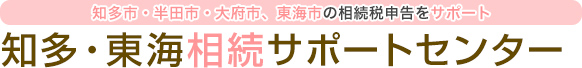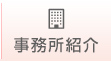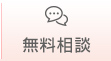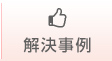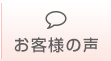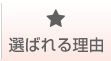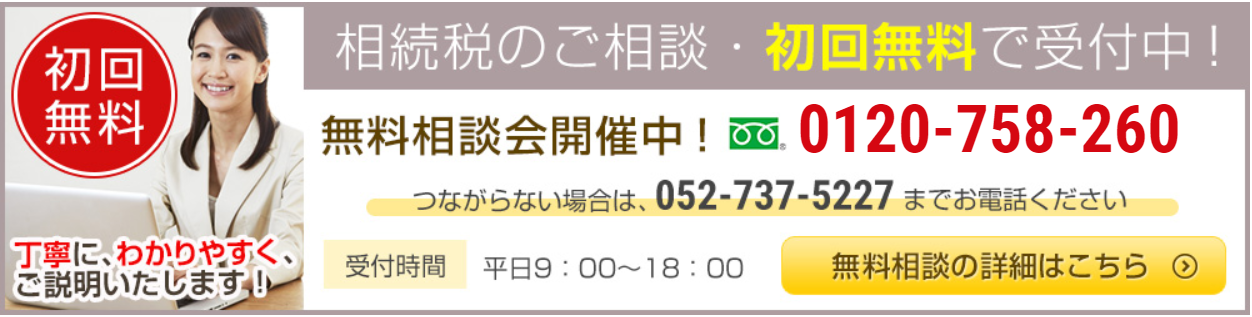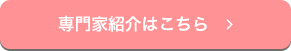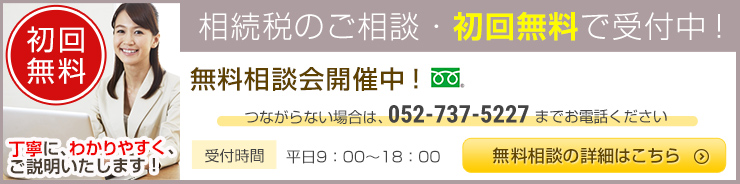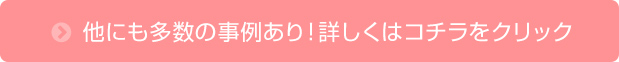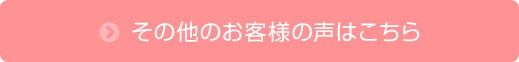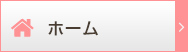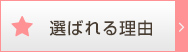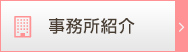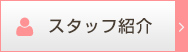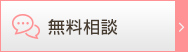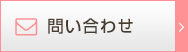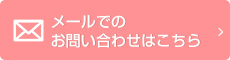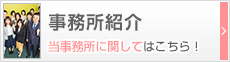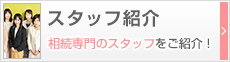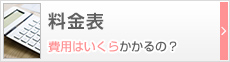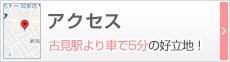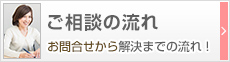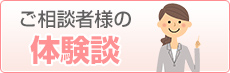相続コラムvol.53「駐車場の財産評価 小規模宅地特例は使える?①」
大小問わず、貸駐車場をお持ちの方は多いのですが、駐車場の評価はどのようになるのでしょうか。
まず、貸している場合には「小規模宅地特例の対象になるか」を検討します。
小規模宅地等の特例の対象となる宅地には4つの種類がありますが、
駐車場はその中の貸付事業用宅地等に該当します。
貸付事業用宅地等とは、被相続人の貸付事業(賃貸マンション、駐車場など)に使われていた宅地のことをいいます。(限度面積は200㎡、減額割合は50%です)
そして条件があります。
取得と保有等の条件
- 相続または遺贈により取得したものであること
- その宅地等を引き継いだ人が、相続税の申告期限までに貸付事業を引き継ぎ、かつ、申告期限まで貸付事業を営み続けていること
- 申告期限までその宅地等を保有していること
- 相続開始前3年以内に新たに貸付事業を始めた宅地等でないこと
*小規模宅地等の特例における貸付事業は、規模については問われません。事業とまでは呼べないような1台だけの駐車場貸しつけであっても、きちんと賃貸借契約が結ばれており、継続して相当の賃料を得ているものであれば問題ありません。
駐車場の形態・契約などの条件
駐車場として使われている宅地の上に、構築物がなければいけません。 構築物とは、土地の上に作られた建物以外の物のことをいいます。
構築物の具体例
- アスファルト舗装、コンクリート舗装、塀、門扉、屋外給排水設備
など
アスファルト・コンクリート敷のもの
アスファルトやコンクリートは代表的な構築物あり、これらで全面が舗装されている駐車場は、全く問題なく小規模宅地等の特例が適用できます。
構築物の所有者は?
駐車場をコインパーキングなどにしている場合には、被相続人は土地だけを貸していて、残りのアスファルト舗装、フラップ板、精算機などはコインパーキングを運営している会社が所有しているということはよくあります。小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、構築物がある駐車場でなければなりませんが、その構築物の所有者が土地の所有者と同一である必要まではありません。
砂利敷の駐車場
砂利敷きは構築物とみなされるので、基本的には小規模宅地等の特例が適用できます。 ただし、砂利が流れてしまい、地面がむき出しになっている駐車場のような場合には、砂利敷きと認められずに税務署に否認されてしまう可能性があります。
確実に特例の適用を受けたい場合には、砂利敷きより費用はかさみますがアスファルトやコンクリート敷きにしておくと良いでしょう。
*1995年に次のような裁決が出ています。
国税不服審判所 平成7年1月25日裁決
被相続人の砂利敷き月極駐車場で小規模宅地等の特例の適応を受けようとしましたが、砂利を敷いたのが約10年前であり、相続開始時点では砂利が地中に埋もれていて、砂利は構築物とはいえない状態になっているとされ、特例の適用は認められませんでした。
空き駐車場
月極駐車場などで借主がおらず空車となっている区画がある場合でも、契約者募集をしているなど空車を埋めるための適切な対策を行っている場合には、その駐車場の全面について小規模宅地等の特例が適用できます。駐車場の場合には空車部分を考慮する必要はありません。
狭い駐車場
1台しか停められないような非常に規模の小さい駐車場の場合にも小規模宅地等の特例が適用できます。(規模は問われません)
賃貸マンションの入居者用駐車場
賃貸しているマンションやアパートに隣接している入居者の専用駐車場は、建物の敷地と駐車場合わせて全体が貸付建付地として評価されるので、貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例が適用できます。
一部だけアスファルトがひいてある場合
駐車場のアスファルト敷きされている部分がすべてがではなく、数台分など一部だけという駐車場もあります。 この場合には、構築物であるアスファルト敷きにされている部分だけに小規模宅地等の特例が適用できます。
ただし、駐車場全体の面積に対してあまりにもアスファルト部分が小さい場合には、駐車場全体に特例の適用ができない可能性があります。
自家用駐車場部分
貸付事業用宅地等に該当するのは、貸し付けをしている部分です。よって、駐車場のうち自家用車を停めている部分については、小規模宅地等の特例は適用できません。
自家用車はどこに停めていますか
自家用車を停めている土地が自宅の敷地と隣接している場合などには、特定居住用宅地等(限度面積330㎡、減額割合80%)として小規模宅地等の特例を受けることができる可能性もあります。ただし自宅と駐車場が道路を挟んでいる場合など分断されている場合では、特定居住用宅地等には該当しない可能性が高くなります。
ケースバイケースでよく検討する必要があります。
大きな減額なりますので、必ず専門家に相談しましょう
この記事を担当した税理士

税理士法人葵パートナーズ
代表社員税理士
花田 直子
- 保有資格
税理士
- 経歴
-
2002年に税理士試験合格。
2011年より税理士法人葵パートナーズの代表社員税理士を務める。
相続の相談件数1,800件以上の経験から相続税を中心とした相続に関する悩みを抱えている相談者からの信頼も厚い。
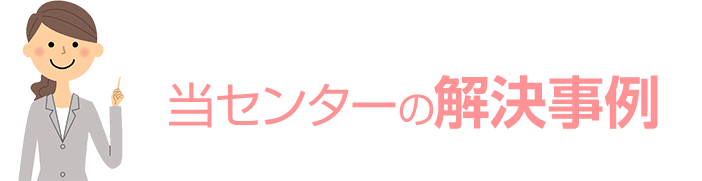
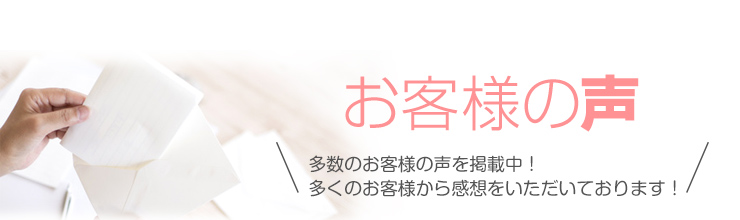
- 2024年7月25日「一度相談に行ってみてください。親切に教えてくださいます」
- ご相談内容:相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 昨年、安島事務所から紹介されて、今回もお願いしました。 2.当事務所のサービスを受けた感想…
- 2024年5月15日「手際よく対応してくださいました」
- ご相談内容:相続税申告 満足度:満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介です。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 手際よく対応し…
- 2024年3月25日「親切で話しやすく合理的」
- ご相談内容: 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 相続の相談でパソコンで検索して決めました。 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? …
- 2023年8月24日「丁寧な仕事で感謝しています。」
- ご相談内容:相続税申告、相続手続き 満足度:とても満足 1.当事務所にご相談にいらしたきっかけを教えてください。 司法書士さんの紹介 2.当事務所のサービスを受けた感想はいかがでしたか? 丁…